人形劇の舞台用語
ケコミ芝居で使われる舞台。つい立状の幕を張った舞台の後ろに、人形つかいが隠れ、人形をケコミの上に出して演じる人形の立っている舞台のこと。
ケコミ(蹴込み)という言葉は、元々は建築用語で、階段の踏み板と踏み板の間にある垂直の板。その言葉が、演劇で使われるようになり、二重などでかさ上げした座敷などの舞台装置で、座敷の下部裏側が観客から見えないように、その側面に張った板のことをいう舞台用語である。形状から連想して、人形劇用語として使用されるようになった。 (→ ケコミづかい)
蹴込みのテスリの左右に、ソデ状の蹴込みを付けて、自立できるケコミ。自立できるので、設営に時間がかからない。ソデ幕なしでも使える。単独でも使えるが、可動パネルと合わせて、本格的なパネル芝居ができる。(→ パネル芝居)
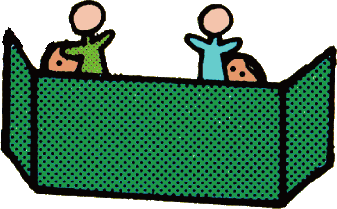
劇の進行にしたがって、移動できるケコミ。
文楽人形のような3人づかいの人形浄瑠璃を演じる舞台。蹴込みの部分は、抱えづかいなので、一般的なケコミ芝居よりかなり低く、人形つかいの足下を隠す程度の高さである。
船という呼称になったのは、川尻泰司によれば、日本の伝承人形が海と深い関わりがあるということである。現在も恵比寿舞のように、人形つかいが船の上から、海岸の観客に向かって演じるものが残されている。
文楽の舞台で、人形つかいが、人形を使う場所。床面より低くなっている場合もある。
ケコミの上辺の部分。人形の演じる地面にあたる。
小道具を置くために奥行き幅のあるものもあるが、奥行きに幅があるとケコミ芝居の特性の仮想の地面で人形が見にくくなったり、ケコミの製作が複雑になるので、幅のないものが多い。(→ 仮想の地面)
ケコミ芝居の概念。ケコミのテスリは、通常、観客の目線よりも、かなり高い位置にある。観客が人形を見る際、人形が舞台の奥に行くにしたがい、人形が地面に潜った状態で見えることになる。そこで仮想の地面を想定し、人形が奥に行くにしたがい、前面にいるときよりも上に差し上げた状態で操作することになる。しかし、人形を持ち上げすぎると観客の目からは、人形が宙に浮いた状態に見える。下げすぎると、人形が地面に埋まったように見える。
テスリの位置が高いほど、その差は大きくなる。さらに、観客の座っている位置によっても仮想の地面は、変わることにも留意する必要がある。前の方に座っている場合と、後方に座っている場合では、仮想の地面が変わって見えるので、会場の奥行きを考えて演技しなくてはならない。特に、人形が小さい場合は、ケコミから離れて演技するのがむつかしくなる。
スソがスカート状の手づかい人形の場合、スソを長めに作っておくことは、この問題を多少は回避できる工夫である。
人形つかいは、人形の地面を想定して、常に演技しなければならない。修練の必要な部分である。
しかし、現在では、出づかいの普及により、仮想地面の概念が、あいまいになっており、以前のように厳格でなくなってきている。
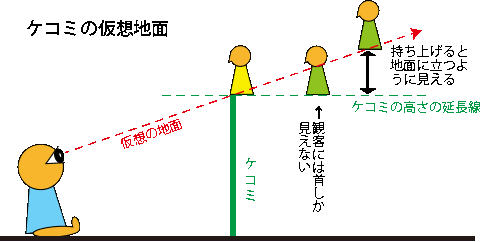
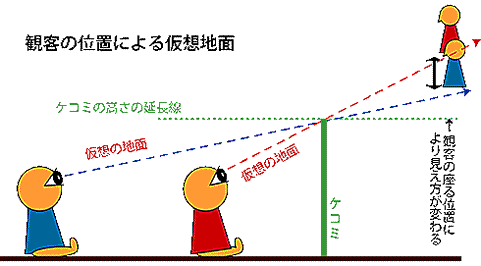
ケコミ芝居での仮想地面の問題を解決するために、メインのケコミの奥に、仮想地面の延長線上に、少し高めの第2のケコミを立てる。観客からは、階段状に見えるので、この呼称がつけられた。場合によっては、さらに複数のケコミを立てる場合がある。
二段ゲコミにより、奥に下がった人形の、足下の隙間を隠す役割を果たしている。二段ゲコミをセットにして、カモフラージュする場合もある。
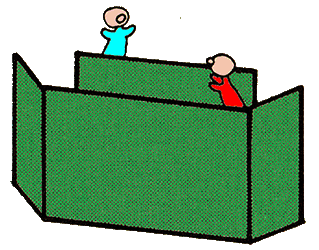
仮想地面を意識して、ケコミの高さを考えねばならない。他に考慮する点は、人形つかいの身長と、天井までの高さだ。
身長については、欧米と日本の考え方に違いがある。身長に差があるのは、もちろんであるが、日本では天井の高さもあり、人形つかいが無理な姿勢をしてでも、ケコミの高さを低く抑えようとする傾向がある。
それに対して欧米では、なるべく無理な姿勢を避けようとするので、当然のことながらケコミは高くなる。さらに最近では少なくなったが、男女の身長差の解消を姿勢の取り方で解決するのでなく、高下駄をはいてでも慎重の高い人に合わせようとする傾向がある。
次に、天井については、欧米と日本では、条件が大いに異なる。欧米の天井は身長のこともあり高い。日本では、当然のことながら低いので、ケコミを高くすると、天井が迫ってくる。人形が演じる舞台の部分のタッパが少なくなり、窮屈な感じとなる。その結果、ケコミの高さは、欧米に比べ、かなり低くなっている。
現在の日本では、ケコミの高さは110cmから140cmの間にあることが多い。欧米では、140cm以上が普通で、自然に立ったまま人形を使うので、実際はもっと高くなる。
かつて、西畑人形や、猿倉人形では、人形つかいが庭に舞台を組み、観客は、座敷に座って鑑賞するという合理的なやり方もあった。しかし、天候のこともあり、屋内で上演することになれば、日本で文楽のような抱えづかい人形が発達したのは、天井の高さが大いに関係しているのではないかと思われる。
舞台装置のこと。ケコミ芝居の場合、人形劇の演じる仮想地面に合わせて、宙に浮いた状態で舞台装置を固定しなければならないので、舞台装置のことを慣習的に〈セット〉と呼んでいる。
ケコミ芝居では、舞台の床から人形の演じるテスリ部分まで距離がある。人形の演じる仮想の地面に合わせるように、セット(舞台装置)を宙に浮かせた状態で固定する柱状の道具。下部はしっかり固定できるようになっている。
ケコミの内側で、人形つかいが舞台装置に接触しないで、自由に動き回れるようにする工夫でもある。(→ アシ)
〈セット立て〉の下部にある、セット立てを固定する道具。木製、金属製のものがある。
アシがしっかりしていないと、人形つかいが接触したときに、セットが倒れたり、揺れたりする。荷物を軽く、コンパクトにするために様々な工夫がされてきた部分でもある。しっかり固定することと、持ち運びの利便性という、相反する課題への解決に苦労してきた歴史がある。
金属製のアシ。持ち運びは重くなるが、セットを安定して保持できる利点がある。
ケコミのテスリの上に小道具を置くと、そのままでは下に落ちてしまうので、設置する台のこと。通常は、蝶番や針金で一方を固定することで、使わないときは、じゃまにならないよう下にたれるような構造になっている。使用するときは、もう一方を柱のように棒で支えるようになっている。
よくできた構造で、支えている棒を、演技者が足で蹴るだけで、セット台は垂れ下がって収納できる。
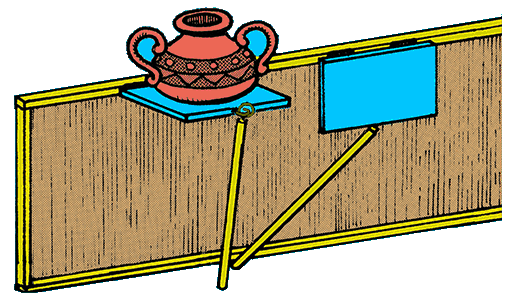
人形劇の小道具を支えたり、操作するつかい棒。
人形劇では、人形が直接持てない場合は、持ち手を付けねばなない。(1) は、最もシンプルな持ち手。(2) は、柄の部分を長めに作っておいて、持ち手にする。(3) は、太い針金で作った持ち手。針金で作るときは、先端が眼に刺さるなど危険なので、必ず丸棒などで先端を太くしておく必要がある。(4) は、フタを開閉する小道具。本体を半丸で作っておいて、持ち手のついたフタが操作できるようにする。
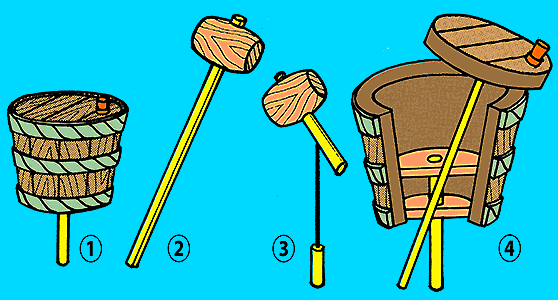
舞台上を自由に移動し、ときには幕の機能を代用する張り物状の装置。下部に、キャスターが仕込まれていることで、移動可能となる。
下図左は、パネル自体がセットになっている。裏面を別の場面のセットにしておけば、素早い場面転換が可能になる。右側は、旅行カバンを利用した、簡単なパネルの作り方。マジックテープを使ってセットを着脱できるようにしておけば、いくつもの場面のセットができる。(→ パネル芝居)
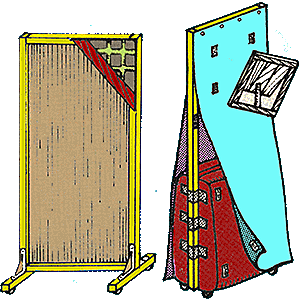
主に舞台ソデなどに置いておき、人形を立てておく台。〈文楽〉では、人形を組み立てる際に使用される。
演劇(人間劇)では、不安定な張り物や、切り出しに固定して、安定して立たせておくための、直角三角形の形状をした支柱のこと。単に、〈人形〉ともいう。
緞帳・幕のいろいろ
舞台の一番前にある幕。芝居の開幕、閉幕に使う。
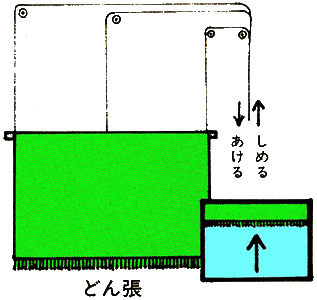
折りたたまれるように開く〈どん帳〉。
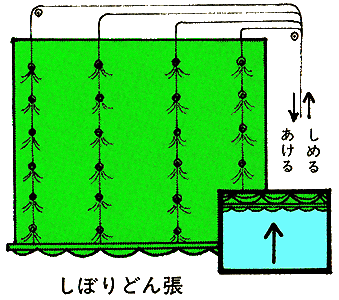
左右に引き割れるように開く〈どん帳〉。単純に左右に開くものと、絞りながら左右に開くものがある。左右に開く〈割どん〉は、〈中幕〉としても使われ、〈中割〉と呼ばれる。
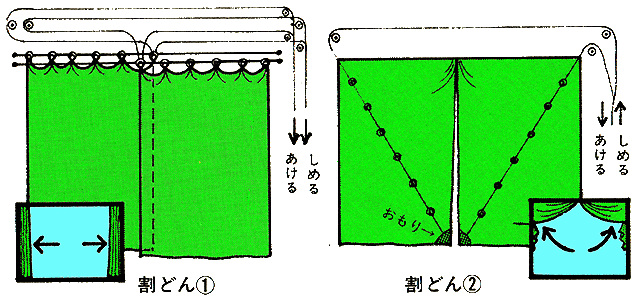
一方向に開く幕。必ず、下手から上手に開かれる。〈どん帳〉や〈中幕〉に使われる。
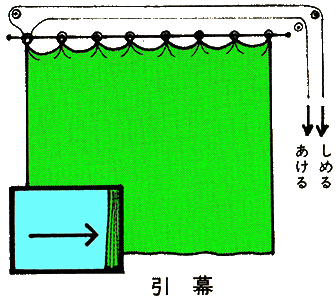
ケコミづかいの舞台
かつては、〈ケコミづかい〉の人形劇で主流の舞台であった。
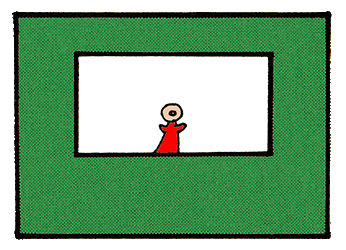
簡便なソデがあるので、わざわざソデ幕を吊る必要はないので、仕込みの楽な舞台。
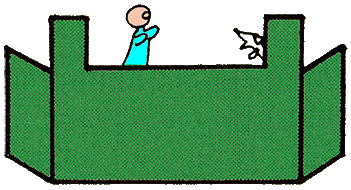
1枚のパネルを使った舞台。パネルには簡単なセットが配置できる。人形の登退場は、パネルの後ろから行うので、ソデ幕の必要がない。キャスターを付けた可動パネルにすれば、パネルをケコミ前に持ってくることで、どん帳の代わりに使える。(→ パネル芝居)
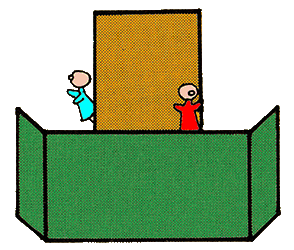
ケコミ部分が張り出しになっているので、観客にとって見やすい舞台となるが、ソデが奥にあるので、入退場の際、仮想の地面が異なるので、人形が沈んで見えなくならように、気を配る必要がある。
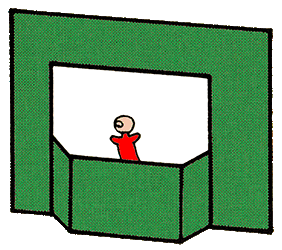
ケコミ芝居の欠点である、仮想の地面を解決するための舞台。(→ 二段ゲコミ)
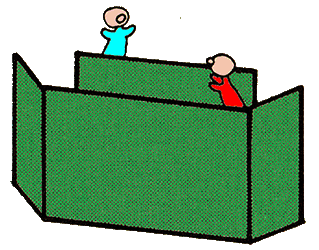
自立できるケコミ。自立できるので、設営に時間がかからない。ソデ幕なしでも使える。 (→ ボックス・ゲコミ)
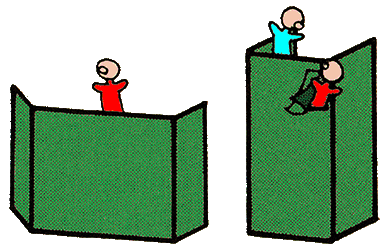
◆ 次のページを見る 【舞台人形の用語】
参考文献 |
「絵で語る人形劇セミナー 4 人形劇は楽しくつくろう」 川尻泰司 1990(1982) |