◆ 舞台用語 ◆
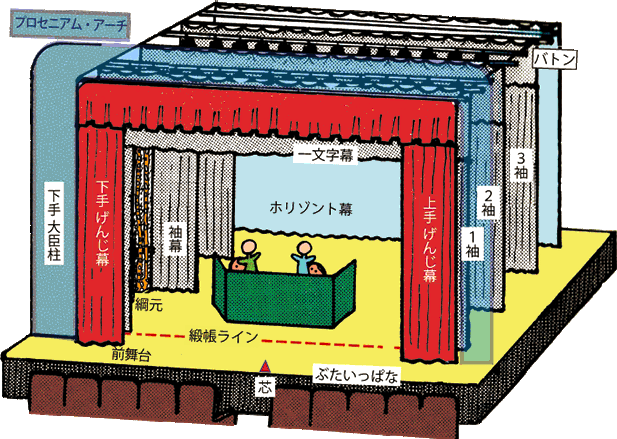
舞台の一番前面の額縁をなすアーチ。どん帳ラインにある。
舞台前面の左右にある柱。
舞台の一番前にある幕。芝居の開幕、閉幕に使う。
どん帳より前にある舞台。
舞台の一部が、客席に向かって飛び出している部分。エプロン・ステージや、ファッション・ショーのキャットウォークなど。歌舞伎の花道を指す場合がある。
一文字幕 (いちもんじ・まく)
舞台天井に吊された細長い幕。照明機材や、吊り物を隠すためのもの。
舞台両脇に設置された黒幕。両脇の奥が見えないように隠す幕。
舞台中程にある幕で、上手、下手に分かれて開閉する。
幕やつり物の上げ下げをする綱のある所。
綱元でバトンや幕を上下する際に、綱の途中に置く重りのこと。これによりバトンや幕の重さとバランスをとることで、小さな力で上下させることができる。ほとんどが、5kgか、10kgの金属製の 直方体の形状をしている。
照明器具、幕、つり物などを取り付けて、綱元で上げ下げできるパイプ。
舞台の一番奥に設置された幕、または壁。通常は照明を当てることで、空を表現するために使われる。
ホリゾントのすぐ前に設置された黒幕。舞台いっぱいに開閉する。上下するものと、左右に開閉するものがある。
暗転幕として、転換時に使うこともある。
舞台天井部分に設置された、格子状のもの。滑車やワイヤーを取り付け、バトンや道具をつり下げるもの。劇場によっては、キャットウォーク(猫走り)やバトンを兼ねている場合もある。
〈葡萄棚〉のこと。 (→ 葡萄棚)
演技者や、道具をのせたまま、奈落(舞台の地下)から上下する舞台機構。セリを少し下げた状態で、ケコミを設置すれば、ケコミの高さを低くして、観客から見やすくできる。
舞台面を高くするための台。基本のサイズは180x90cmであるが、様々なサイズがある。二重ともいう。
ケコミなど、人形劇のための舞台を組まずに、平らな舞台で人形をつかう場合の用語。出づかいが発達したことで、よく使われるようになった。
舞台位置の用語
観客席から見て、舞台の左側。欧米では、舞台から観客席を見て右手という。
下手は、観客の印象が親しみやすい性格を持つので、原則、司会者などが立つ位置になる。また、登場が自然な感じに見える効果もある。
観客席から見て、舞台の右側。欧米では、舞台から観客席を見て左手という。
日本では、上手は上位の席の意味合いがあるので、ゲストなどが立つ位置になる。また、上手の登場は、やや違和感のある感じに見えるので、突然駆け込んでくるなどの効果で使われたりする。
舞台の間口の中心。舞台の準備をする際の基準になるライン。舞台設営の際は、最初にテープで印を付けてから作業を始める。
特に、会場がシンメトリーでないときには、舞台監督が客席から見た感じで、芯を決める必要がある。
芯を決めずに舞台を作ると、後で、すべての位置を調整し直すことになるので、芯決め(しんぎめ)は重要な作業である。
舞台装置や、小道具を置く定位置、または演技者の立つ定位置のこと。(→ アタリ)
〈居所〉に、テープなどで印を付けること。
舞台装置や、小道具を置く定位置、または演技者の立つ定位置のこと。素早い転換のために、あらかじめテープなどで印を付けておく。
照明では、スポットライトの位置決めをすること。
テープなどで、アタリの印を付けること。「場見る」からきた言葉と思われる。 ( → 居所当たり)
上下(かみしも)の大臣柱の間長さで、舞台の基本的な幅になる。
上下(かみしも)のソデ幕によって、客席から隠された場所。
ソデより内側にある奥の部分。転換のための舞台装置や人が隠れる部分になるので、ふところに余裕があるかどうかは重要。
床から天井までの高さや、舞台装置の床からの高さのこと。
舞台の上手と、下手の性質
舞台の上手と下手は、位置を指示する用語だけでなくそれぞれにに与えられた性質があります。日本の文化からくるものと、生理的な要因から起因する性質があります。
まず、日本では、文化的伝統で上手・下手に、それぞれの役割が決められています。最近は、意識されることが少なくなってきましたが、これが守られないと、「常識知らず」ということになってしまいます。
上手は、古来身分の高い人の座る位置だったのです。左大臣などが、上手に座ることになっていたことによります。つまり、天皇の左側に左大臣は座ることになっていたのです。観客側から見ると上手になります。座る位置によって、一目で身分の序列が決まっていて、従来は、厳格に守られていた歴史があります。
したがって、司会が上手から登場することは、潜在的に違和感を感じるのが日本人です。司会者は、潜在的に下座にいるべきという感覚があるからです。
ほかに、文化の伝承だけでなく、人間の生理学的な特徴から起因している側面もあります。人間の目は、左から右に対象物を追いかける性質があります。
横書きの文書が自然に読めることでわかると思います。したがって、アラビア語のように右から左の横書きには、違和感を感じるのです。試しに、目玉を左から右に動かすのと、反対に目玉を右から左に動かすことを試してください。どちらがスムーズか感じられるでしょう。大抵の方は、左から右になるでしょう。
日本語の漢字の額で、右から左への横書きが見受けられますが、これは、横書きでなく、1行に1文字の縦書きなのです。1行が1字詰めの原稿用紙を想像すれば、容易にわかると思います。昔の日本人は、横書きの意識はなく、縦書きで読んでいたので違和感はありません。
私たちが違和感を持つのは、早い時期から西欧式の横書きに親しみ、なじんでいるからです。昔の人には、横書きの概念はありませんでした。横書きのように感じるのは、後年の私たちが、勝手に勘違いしているだけで、縦書きの書式しかなかったのです。
少し横道にそれました。話しを戻しましょう。人間の目の動きが左から右に流れる性質により、下手から上手に登場する人物は、自然な動きにとらえられ、親しみやすい印象を観客に与えるのです。そのことから、司会が、下手から登場することが作法となっているのです。NHKの紅白歌合戦の司会席は下手に設けられていますよね。
逆に、上手から登場する人物は、殺人者だったり、突然のしらせを持ってきた人物の登場に使われるのです。つまり、上手からの登場は、人間の生物的特性を逆なですることで、登場人物の異常な性質を本能的に観客に与える効果を狙って表現されているのです。
以上のことから、上手・下手は位置の違いだけでなく、舞台上の意味合いが異なることを留意する必要があります。
舞台装置の用語
舞台を構成する基本的な装置や、セットなど。
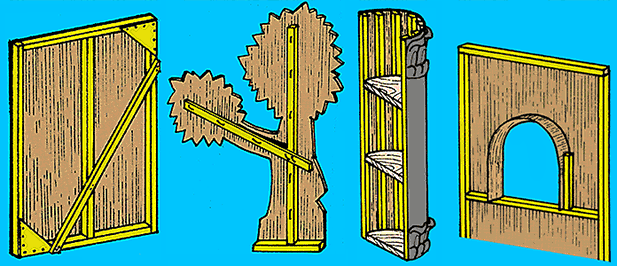
舞台で使われる小形の道具の総称。
小道具のうち、持ち運んで使われる物。
小道具のうち、飲食物や、燃やす、こわすなどして消耗される物。
木などのワクに、紙、布、ベニヤなどを張った舞台装置。
ベニヤなどを形に切り抜いて彩色した舞台装置。
下図のように、建物の上半分を折りたたむと、花の生け垣に変化する仕掛けのついた切り出し。
つぼみの生け垣の下半分の裏側に、花の咲いた生け垣の上半分を描いておいて、垂れ下がった下半分を引き上げると、花の咲いた生け垣にすることができる。
素早いセット転換ができるので、〈明かる転〉の有効な手段。
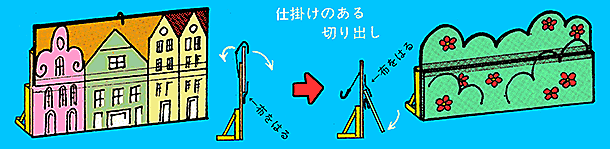
切り出しなどの裏を、材木などで補強する作業。
切り出しの窓のセットなどで、窓枠に立体感を出すためのもの。
大道具、小道具、人形で、立体的に作られた物。
大道具、小道具、人形で、見える部分だけ立体的に作られた物。
バトンに吊して、上下させる大道具。
バトンなどに吊された布製の舞台装置。人形劇では、ケコミに掛ける布製の舞台装置こともいう。
舞台裏を観客から隠すための張り物。または、舞台裏や、隠れているべきセット・人形等が観客席から、見えてしまっていること。
舞台装置の窓、ドアなどを開けたときに、舞台裏が見えないように置かれた張り物。
二重などでかさ上げした座敷などの舞台装置で、座敷の下部裏側が観客から見えないように、その側面に張った板のこと。人形劇の場合は、〈ケコミ〉と呼ばれ、人形つかいが隠れるための衝立や幕。(→ ケコミ)
舞台裏を観客から隠すための張り物。または、舞台裏が観客席から、見えていること。
人形、大道具、小道具などを、古びた感じや、立体的に見えるようにするために、影をつけるように色を塗ること。
舞台準備の用語
上演を可能にするための、すべての準備をすること。
大道具、小道具を舞台上に、配置すること。
舞台の前から奥に向かって、次第に高く道具を飾る方法。または、傾斜した台。
終演後、舞台を解体し、かたづける作業。
舞台関係者が、会場や舞台に到着すること。
入りの時に、舞台・芸能関係者が用いるあいさつの言葉。
元々は、歌舞伎の世界で、遅れて入ってきた座頭が、座員へのあいさつとして使われた。朝という意味はなく、「お早くから、ご苦労様」の意味合いで使われた。現在では、上下の関係なく広く、入りのあいさつとして使われている。
舞台進行の用語
開演の予鈴。通常5~15分。会場の広さによって異なるが、観客が無理なく全員が席に着ける時間を確保。
年齢の低い観客が主体の場合は、全員の着席があったら、すぐ開演できるタイミングを計って鳴らすので、人形劇の場合は、短い時間を設定する場合が多い。
開演の合図のベル。
最近の傾向としては、ベルが耳障りなので、本ベルを省略した演出も多い。本ベルの代わりに、オープニングの音楽を流し、自然なかたちで開演する。
上演時間などが、予定している時間より伸びること。
上演時間を予定の時間より早めに始めること。あるいは、舞台進行の時間を遅らせないで、割り込んで何かをやることや、道具の位置を演技がしやすいように、気づかれない程度に移動する場合にも使われる。
照明を暗くして、舞台転換を行うこと。
照明を暗くない状態で明るいまま、舞台転換を行うこと。明るさは、様々ある。(→ 照明:明かる転)
演技者の動作や、セリフなどの間。動作や、セリフを際立たせる効果がある。「間が悪い」「間が抜けている」の語源となっている演劇用語。
幕が開いたとき、すでに舞台上に出ている人形。
開幕直後に登場するために待機している人形。
不要になった道具を、舞台天井部分に吊り上げ隠すこと。
不要になった道具を、かたづけること。
一度使用した人形や道具を、別の目的で再び使うこと。
シーンごとに、横軸にシーンの名称、縦軸に担当者名を書き、何をするのかを時系列に表にまとめたもの。(横軸、縦軸は決まっていない)人形劇では、同じ人形を場面によって違う者が演じる場合がある。人形劇では、キャスト、スタッフの役割が明確に区分されることが少なく、場面転換のときには限られた時間で処理しなければならないので、〈香盤〉は必須アイテムである。(→ 香盤の例)
舞台進行で、動作や転換の合図のこと。転じて、合図をすること。もともとは、歌舞伎用語。照明や音響では、キュートいうこともある。略して〈Q〉と表記する。
稽古、または上演後、キャスト、スタッフに注文を出すこと。基本的に演出が〈ダメ出し〉をする。上演に入っているときで、演出不在の際は、舞台監督が行う。
◆ 次のページを見る 【人形劇の舞台用語】
参考文献 |
「絵で語る人形劇セミナー 4 人形劇は楽しくつくろう」 川尻泰司 1990(1982) |