「人形劇クリニック」って、なに?
● 人形劇作りの講習会?
人形劇の「講習会」というと、時間が限られているせいもあって、人形作りで精いっぱいということになり、人形の操作に時間をかけるのが、むつかしくなるのが現状です。結果、人形劇の講習会なのに、人形劇のおもしろさを、充分に伝えることができないというジレンマを感じていました。
最近は、工夫してなるべく簡単に人形を作ってしまい、人形のつかい方に時間をかける工夫をしている方も見かけるようになりました。しかし、ある程度ちゃんとした人形を作ってやりたいという、欲求を犠牲にすることにはなります。
自治体などの援助を受けて、いくつもの「初心者のための講習会」というのも経験してきました。そこでは、10回とかの時間の中で、人形作りからはじめ、人形の使い方の練習も充分に行い、発表にこぎつけることができます。講座の終了後、せっかくだからといって、参加者が人形劇団を立ち上げることになることが、少なくありませんでした。場合によっては、最初から、人形劇団を作るための講習会だったりもします。
しかし、終了後は、指導ははいなくなりますから、あとは何もかも自分たちでやることになります。練習時間も充分とって稽古にはげんでも、やがて「これ以上なにをやったらいいんだろう?」ということになります。プロの人形劇団の公演を見に行ったり、ほかのアマチュアの人形劇団に話を聞いてみたり、努力はするのですが、やがてマンネリ状態におちいってしまう、というのが一般的な傾向です。
その結果、残念なことに3年くらいで、解散ということになってしまいます。なかには、私の知らないところで、25年も続いていたことを聞いて、驚いたこともあります。けれども、それはとても希なことです。
何とか、人形劇の楽しさを体で感じてもらえるような、指導はできないかということを、ずっと考えていたのです。人形作りをしなければ、人形を動かす練習に、すべての時間をさくことができると考えて、「クリニック」という考えに思いいったのが1980年代後半のことです。
● 人形を作らない講習会!
すでに、お持ちになっている人形を使ってのの、指導メニューを考えたのです。人形をつかって表現する楽しさを伝えることができるし、人形の改良点も実地に指導することができるので、一石二鳥というわけです。クリニックというのは、プロの人形劇団の人に、自分たちの上演を見てもらって、感想をいってもらうということではありません。私なりの指導プログラムの元で実践的に、指導を受けるということです。
音楽を習うなら、演奏家のプロから習うより、指揮者や、作曲家に習った方が楽しい、といのが私の持論です。私が、歌や楽器が得意でないといういい訳かもしれませんが。
演奏家は、指揮者や、作曲家からの要求を実現するために、日々自らの演奏の可能性を広げる訓練をしています。したがって、演奏家による指導は、表現の可能性を広げるための注文が、厳しくなりがちです。一方、指揮者は、どんなにがんばっても自分が演奏するわけではありませんから、どんなに不十分な技量であっても、演奏してもらわねば、自らの表現はできないのです。したがって、演奏者の長所・短所を生かした指導をいつも考えていることになるのです。
これが、私の指導プログラムの要というわけです。
対象は、活動しているアマチュア劇団だけでなく、作品として上演していなくても、現場で人形を使っている保育者や、教員の方のプログラムもあります。
全国どこにでも出かけますので、ぜひ体験してみませんか?
藤原玄洋 2004.11.14
人形劇クリニックのメニュー
● アマチュア人形劇団のためのクリニック |
|
 |
現在上演している作品を、グレードアップするためのクリニックです。 まず一度、上演いただいて、その後、人形操作、演出、美術、音響、照明、稽古の進め方など、具体的に指導します。 できるだけ、現在できているものを生かすかたちで、指導します。 |
1劇団 1回 3時間 |
|
● 保育現場ですぐ生かせるクリニック |
|
 |
各自、人形を1体ずつ持ってきていただきます。舞台人形が(人形劇用の人形)ないときは、オモチャのぬいぐるみでも結構です。 5~8名の班分けをし、即興的に5分程度の、人形劇をその場で作ってもらいます。 各班で、上演していただきます。 各班ごとに、人形操作、劇の作り方(特に場面転換)について指導します。 ほかの班の方は、指導の状況を見ていただきます。 自身が指導を受けるだけでなく、他の方の指導を見ることで、より深く理解が深まります。 人形舞台は、当方が用意します。 |
40名まで 1回 2~3時間 |
|
● 人形作りから上演まで |
|
 |
最終的には、地域のアマチュア人形劇団を立ち上げることをめざします。 20分くらいの作品を、参加者全員で作ります。 ◆ 「いろいろな人形劇」「上演までの作業の進め方」の話。 ◆ 台本の配布。 ◆ 「人形のデザイン」の話。人形作り開始。 ◆ 人形作り。セリフの稽古。 ◆ 人形作り。素立ち稽古(人形を持たない立ち稽古)。 ◆ 人形操作の稽古。舞台装置を作る。 ◆ 立ち稽古。「照明」「音響効果」の話。 ◆ 立ち稽古。「音響効果」の準備。 ◆ 立ち稽古。「制作活動(上演場所の探し方など)」の話。 ◆ 立ち稽古。「劇活動の維持の仕方」の話。 ◆ 舞台稽古。上演発表。講評。 講習の回数により、人形の種類や、台本の長さが変わります。 |
15名まで 10回程度 1回2時間(宿題あり) |
|
● 簡単な人形作りと人形の動かし方 |
|
 |
簡単な人形を1時間くらいで作ります。 その人形を使って、2~3分くらいの作品を作ります。 作った人形は、各自でもって帰れます。 ◆ 「ぱくぱくガエル」を作って、「カエルの合唱」を演じます。 ◆ 2本の糸で動かす犬の「ワン君」を作って、「ワン君の散歩」。 ◆ 人形作り。セリフの稽古。 ◆ うちわ型の立ち絵人形を作って、「森のクマさん」のボードビル(音楽に合わせて演じる人形劇)。 |
15名まで 1回 2~3時間 |
|
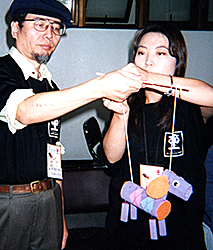 |
|
略 歴 : 藤 原 玄 洋 略歴
(ふじわら・げんよう)
1948年
・神戸に生まれる。
1967年
・岡山大学人形劇部に入部。'69年に県文化センターホールにて、部としてはじめての学外自主公演を組織する。
1968年
・岡山県人形劇連絡協議会事務局長。県人協を代表して全日本人形劇フェスティバル[旭川] に実行委員として参加。
1970年
・大学在学中より高知県発祥の伝承人形劇「西畑(さいばた)人形芝居」西畑人形座の仕事を手伝う(制作・人形操者)。
1971年
・人形劇団プークの川尻泰司の指導で、伝統人形劇を母胎に、現代人形劇をも取り組む人形劇団として、「人形劇場たけのこ」(代表:池原由起夫)の創立に参加する。
・旗揚げ公演「1ぱつ9のごうけつハンス」[作・演出・美術:川尻泰司、岡山県総合文化センターホール、5月]で、俳優、舞台監督を担当。
・日本ウニマ(国際人形劇連盟)会員となる。
1973年
・所長川尻泰司氏の勧めにより、日本人形劇研究所に入所 (現職)。
・人形劇団プーク45年史編纂委員に就任('76年まで)。
・人形舞台エミのための川尻泰司の作品、「八郎」('75年)、「こぐまのコロンくん」('76年)、「パンは誰のもの」('77年)などに舞台監督として参加。
1975年
・千代田工科芸術専門学校放送芸術課程の非常勤講師(人形劇ゼミ)となる('92年まで)。
1976年
・第12回モスクワ世界ウニマ大会に参加。人形劇場たけのこ「岩見重太郎大蛇退治」の舞台監督を務める。
1979年
・アジア・太平洋国際人形劇祭典 東京祭典広報宣伝委員を務める。 1983年・NHK教育番組「人形劇の秘密」(全5回)の構成台本を執筆。
・人形舞台エミのソウル公演「三びきの子ブタ」の舞台監督を務める。
1984年
・第14回ドレスデン世界ウニマ大会参加、NHKでその紹介番組の構成。
1987年
・創立50周年記念PofA(アメリカ人形劇人協会)フェスティバルに日本代表団団長として参加。翌年の世界ウニマ大会のアピールを行う。
1988年
・第15回世界ウニマ大会[名古屋・飯田・東京]で、活動企画委員を務める。
1989年
・日本ウニマ幹事に就任('01年まで)。企画財政委員長を務める。
1990年
・第1回人形劇学校の教師による国際会議[フランス:シャルルビル・メジェール]に、国際交流基金の助成で出席。
1992年
・日本ウニマ常勤事務局員 (2001年まで) となる。
1994年
・川尻泰司記念日本人形劇研究所に改組、事務長となる。
1999年
・GEN人形劇クリニックを設立、主宰する。
2003年
・日本ウニマ幹事に就任。アマチュア委員会委員長、電子情報委員会委員長。
・アジア一人劇祭[韓国:公州市]で、ワークショップの講師を務める。
2004年
・クロアチア総会で、世界ウニマ評議員に選出される。
主な劇作
・「タン平くんとコン吉くん」 1976年初演
・岡山の昔話「ねずみ経」 2001年初演
・千葉の昔話より「田んぼの茶屋」 2003年初演
主な著作/編集
・「日本の人形劇」日本ウニマ年鑑の1982年版から「人形劇関係の図書雑誌カタログ」を毎年執筆。
・「玉川学校劇辞典」[玉川大学出版 1984]の人形劇の項執筆。
・小学館「百科事典ジャポニカ」の人形劇の項、川尻泰司と共同執筆。
・その他、川尻泰司の著作「日本人形劇発達史・考」[晩成書房]、「絵でかたる人形劇セミナー(全4巻)」など多数を編集。