文楽人形の用語
この項は、「阿波十郎兵衛屋敷」のホームページを参考にした。
三人づかいの人形浄瑠璃などで、人形の首と右手をあやつる操者。高下駄を履くことで、人形を高くし、足遣いの操作を助ける。
三人づかいの人形浄瑠璃などで、人形の左手をあやつる操者。主遣いの操作の妨げにならないよう、差し金をによりあやつる。
三人づかいの人形浄瑠璃などで、人形の足をあやつる操者。
上演される人形芝居の演目名。
人形芝居の芸題のうち、歴史上の人物や事件を扱った作品を「時代物」という。主に五段構成で作られる。これは能の五番立てから発したといわれている。
江戸時代は、徳川家や当時の事件・実在の人物の脚色を禁じられていたため、作品の時代や登場人物を室町時代より前に設定して上演された。そのため、源平合戦や戦国時代の武将にまつわる出来事などが題材として多く描かれている。平安時代より前を扱った作品を特に「王代物(おうだいもの)」と呼ぶ。
江戸時代の町の人々の生活や風俗などを背景とした作品を「世話物」という。通常、上中下の三巻で構成される。
庶民の恋愛模様や町中で起きた事件などを題材にし、時に、実名のままで上演される場合もあった。写実味の強い作品を特に「真世話(ませわ)」と呼ぶこともある。
〈景色事〉の略。音楽,舞踊を主とする部分、および、そこで演じられる演奏、演技の種類をいう。
音楽 (浄瑠璃) 面に限る場合は、節 (ふし) 事ともいう。5段物の時代浄瑠璃には,通常4段目の初めに,景事の代表である道行の場がおかれ、世話浄瑠璃では心中道行などが設けられる。
ほかにも音楽的、舞踊的表現によって観客を陶酔させ、劇的緊張をやわらげるために、「…尽し」「…物狂い」などと呼ばれる景事場面が設けられることが多く、『義経千本桜』〈道行初音旅〉、『心中天の網島』〈名残の橋尽し〉、『芦屋道満大内鑑』〈小袖物狂い〉などが有名。なお、上方では、歌舞伎の所作事も景事と呼んだ。
現在、上演される文楽作品の多くは江戸時代に作られたものだが、明治時代以降も作品は作られている。
これらを特に「新作」といい、明治時代には、現在でも上演されている『壺坂観音霊験記』『勧進帳』などが作られた。今でも、その時代に合った言葉・内容で、幅広い世代に向けて作られ続けている。
文楽人形の舞台
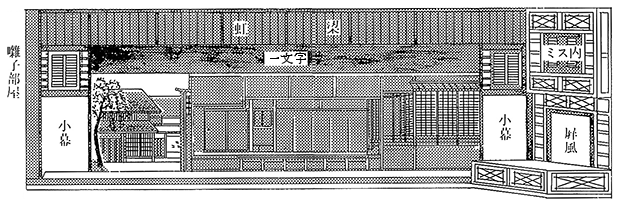
→ 舞台全図を見る 太夫床
三人づかいが完成し、人形の大ききも決まるとともに、舞台の構造もほぼ現在の様式に確立した。
国立文楽劇場の例でいうと、舞台の間口は約7間半(13.5m)、舞台端から約1間(1.8m)、奥から幅7尺(2.1m)位の部分が、舞台間口いっぱいということになる。約1尺2寸の深さに落ちこんでいて、これを〈船底〉と呼び、一般の演劇で平舞台にあたる場所。
その奥は、元の舞台面の高さで、〈本手〉といい、一般の二重にあたる。大道具の飾りつけは、船底の前面に、1尺6寸の前手摺、後面に2尺8寸の後手摺を立てる。前手摺の少し前に、8寸高の黒いシゲザンを立てる。手摺は前から順に一の手、二の手、三の手と呼ぶこともある。
つまり人形つかいの立っている床面から2尺8寸の高さが、人形の足の位置で、地面あるいは床面ということになる。人形の構え方が高くても、低くても、人形が宙に浮いたり、地面にめりこんで見えるので、絶えず一定の高さに保たねばならない。しかし、大きな人形だと20~30Kgもあるので、容易なことではない。人形つかいの左手には必ずタコができているのも、このためである。
人形が、本手(二重) と 船底(平舞台)を自由に往来できるように、本手の手摺りに出入り口がつけてある。これをオトシと呼ぶ。
オトシの幅は約120cmだが、3人の人形つかいが、無理なく通れる最小限の寸法である。ノレン口の幅なども同じ。
オトシには、観音開きや、左右に引くなどいろいろの形式がる。陣屋などの三段や、御殿の階段などは、中央から左右へ割れるようにできている。オトシの開閉は大道具の係になっている。
現在の文楽では太夫、三味線は出語りが原則。大序や、ごく短い端場の場合は御簾のなかで語る。
御簾内の場所は太夫床の上にあり、御簾の中央には櫓下の太夫名が大きく書かれる。現在は櫓下がないいので劇場名を書いている(東京の国立小劇場は床の上に御簾がないので、上手小幕の上の御簾を代用している) 。御簾内の場合は肩衣はつけない。
舞台の船底の両端にある人形の出入口を、小幕と呼んでいる。歌舞伎の揚幕のような黒い幕がつるされていて、幕の中央には竹本、豊竹両座の座紋が白く染め抜かれている。小幕の上は左右とも御簾がかかっていて、上手は御簾内の太夫座、下手は囃子部屋にあてられる。
出語りの床は舞台の上手に、客席の方へ斜めに張り出していて、歌舞伎の回り舞台と同じく廻るようになっており、太夫と三味線の交代をする時に使う。背面のついたては、表面が金、裏面が銀で、切場のときに金が出るようにするのが通例だが、場数の関係でそのとおりにならない場合もある。
廻りになっている床を、文楽まわしと呼ぶこともあるが、おそらく歌舞伎のチョボ床から出た呼称だろう。この形式がいつごろ始まったかわかないが、以前は前に御簾が下がるようになっていて、太夫の交代のたびに御簾の上下をしたようである。現在も地方公演などで、本式の床がない場合は、御簾が使われている。
床の出語りには必ず太夫、三味線は肩衣をつける習わしで、肩衣の紋所は太夫のものと決まっている。たとえ、三味線が先輩でも太夫の紋所のものを着るので、肩衣は太夫の持ち物となっている。
文楽人形の構造
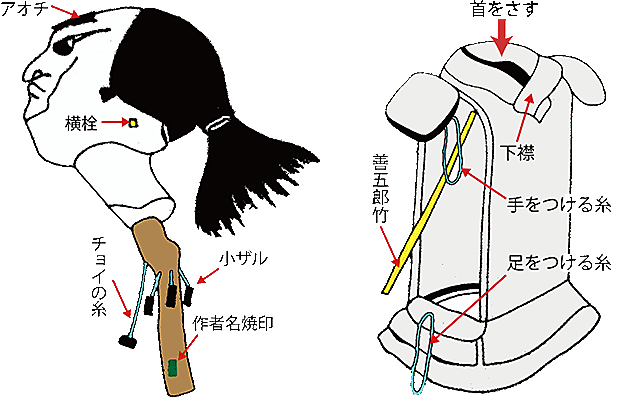
首のクビの部分。首と胴串を結ぶところで、胴串の引糸が喉木を経て首に通じ、上下に動いたり正面を切ったりする。
喉木を通って、首を動かす糸。首を上下に動かしたり正面を切ったりする。
首の耳の下あたりで、水平に首と、胴串を通す竹串のこと。人形がうなずくときの軸になっている。肩台に胴串を固定するときにも使われる。
首の内部に製作者名、製作年月日などが書かれているもの。明治以降に製作された首に多く見られる。
喉木や胴串に押してある人形師の焼印。首の製作者の証となる。他の人形師の作品を補修した際の焼印もある。
胴の内部にあるつかい棒で、突き上げることで、人形の肩を上下させ、息づかいなどを表現する。〈つきあげ〉と呼ぶこともある。
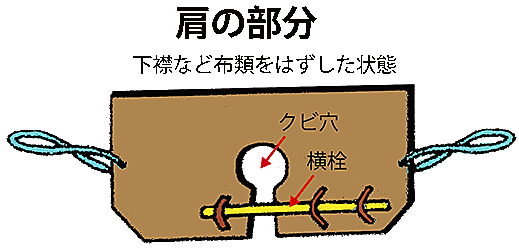
胴串を通して、人形を組み立てる。切れ込みがあるのは、小猿などの仕掛けを通すため。胴串を通した後、横栓をを通して固定する。
曲の糸。頭のウナヅキと目や眉、口などを操る糸で、胴串の引栓または小猿につながっている。
胴串にあるトの字型の引っ掛け。胴串の細長い溝にはめ込まれており、これを下へ引くと引糸が首を動かす。
人形をうなずかさせる引糸の先に、結んだ玉状の引き手。和紙を小さく巻いて作る。
手は桧などで作られ、右手は小猿、左手は差金によって動く。つかみ手、たこつかみ、狐手、三味線手など役柄に応じて多くの種類があり、首とともに人形芝居で重要な働きをする。
指で革製の関節がついていて、手を握ったり、開いたりすることのできる手。
つかみ手で、手を握ったり、開いたりする動きのための糸。
指に関節のない手のこと。手首が動くようになっているものもある。
人形が、手で物をつかむときに、物を差し込んで固定する革製の輪。
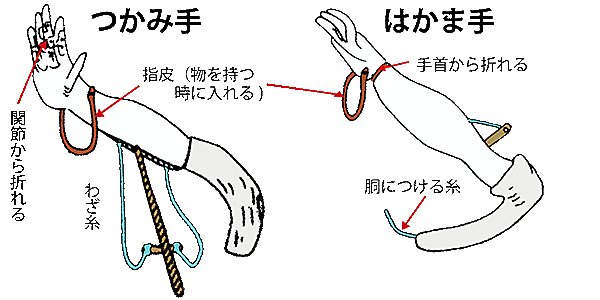
足は大、中、小に分けられ、脛と足は木、股は張子か布でできている。
踵の上に取りつけた金具をつかんで、前後左右に動かすことで歩く動作を表現する。女の人形には使わないのが通例で、足の無い場合は足づかいが着物の裾を握り、足のあるようにつかって見せる。
人形つかいの修行は、足づかいからはじめて、左(手)つかいへと進みむ。「足10年、左10年」で、昔は一人前の主づかいになるには、20年かかるとされていた。
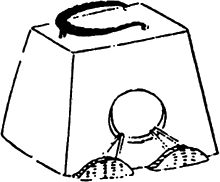 |
下駄は、主づかいが人形とつかう時にはく。主づかいが、足づかいが楽な姿勢で操作できるように、人形を高く差し上げるためのもの。 高さは15~30cmぐらい、滑らないように、底にしっかりとわらじをゆわえてある。片方の下駄に1足のわらじを使う。下駄は、主づかいの権威のシンボルで、1人の主づかいに、大小いろいろの下駄が用意されている。 |
 |
文楽の人形では、役柄に合わせ、首、手、足などの部品を組み立て、衣裳を着せることで作られる。その際、人形を立たせておくための台。現代人形劇とは異なり、 一役首以外 のものは、首を含め使い回しされる。 |
衣裳が肩の部分からつり下がっていいるだけでは、ぺちゃんこになって見えるので、腰のアタリを膨らませるため、竹の輪に衣裳固定することで、立体的に見せる。(→ 人形立の写真参照)
文楽人形の首の用語
人形芝居の中で、主役を演ずる役柄。その首を立役首という。。
→ 文七首の画像
女の人形に使う首、または役どころの名称。小娘、娘、女房、婆、お福など。
→ 女形首の画像
弱い者をいじめる憎々しい表情をした首、または役どころの名称。『彦山権現』の京極内匠などに使われるので〈内匠首〉ともいう。
→ 寅王首の画像
詰端首の略。一緒に詰め込まれる端役の首の意。百姓、町役、奴など。
→ 男のつめ首
→ 女のつめ首の画像
首(喉木)が頭部と一体に作られていて、上下に動かない首。雑なつくりで、端役の人形に用いられる。
文楽の首は、役柄に応じて使い回されるが、一役首は、特定役のために特別に作られた首で他の役へ使いまわさない。
大江山の酒呑童子や玉藻前の妲己など。
→ 一役首の画像
一役首のこと。 → 一役首
眉は動くが、目はつむるだけでカッと見開くことができない首。
眉が動き目や口を開け閉じする首。顔に品があり二枚目役に用いられる。『太功記』の十次郎、『一谷』の敦盛など。
首の表情の動きのことを曲という。目の開閉、眉の上下、口の開閉、目の左右など総ての曲が用いられている首を総曲という。
人形の糸の仕掛けで操って、顔の表情を動かす装置のこと。このカラクリを曲ともいう。首の曲の数によって二曲首とか三曲首とかいう。
人形の頭髪のこと。鬘には時代物と世話物との区別があり、髪形によって役どころがわかる。その種類は男女とも多様あり、まさかり、百日などの名称で呼ばれる。
首にはめ込まれた、水晶、珠玉、ガラスなどで作られた眼を。
人形の目を閉じる動きをいう。眼球を上下に回転させて白目の中に一文字の筋を引く。泣く動作に伴うもので、眠るわけではない。目をつむる仕掛けはバネで、鯨のヒゲが使われるが、ステンレスのものもある。
両眼の瞳が鼻柱に向かって引き寄せられる動き。眉の動きを伴い、忿怒、悔根、決意、威嚇などを表現する。
目の左右の動きで、左右いずれかへ、同時に2つの瞳が動く。特定のものを見たり、流し目や蔑視、憎悪の表情に用いられる。
目玉がひっくり返る仕掛け。胴串の糸を引くと眼球が上下に回転し、異形・妖怪の相となる。常に顎落ちと併用される。
人形の眉が立ちあがる動きをいう。眉根から頭の内部を通り、胴串まで伸びた糸を引くと、眉尻の方が弧を描いて立ちあがるように動く。
眉全体を上げ下げする仕掛けのこと。眉の形に切った金属板の眉根が、人形の額に刻まれた縦溝にそって上下する。 上下に動く眉をアオチといい、怒った表情などを表現する。
眉形に切った金属板に張りつけた毛の眉。この眉は強い性格の顔を表現する。
人形の顔に、眉毛を直接に張った眉。描き眉と同様に動きはない。
人形の顔に直接に描いた眉。動きのない首で、女形のほとんどが描き眉である。
眉尻がとてつもなく下がるカラクリ。鼻返りと連動しており、滑稽な役に使われる。下がり眉、眉落ちも同じ。
眉下がりのこと。(→ 眉下がり)
眉下がりのこと。(→ 眉下がり)
役柄を強調するために紅、青、墨などの絵具で一定の型に顔面を彩色すること。目や鼻などを強調する〈勢〉とは異なる。
目や鼻の特徴を強めるため、その周辺に施された線描。目尻に裂線を鋭く描き添えて目のするどさを強調するなど。
人形の顔面、頬骨の下などに施された細い曲線。苦悩する老人の相貌を表現する。描き皺と彫り皺がある
顔面を顔料で塗らずに、縮緬の布を張った首。武勇の士の死相をよく表現した景清などに使われる。
人形の鼻動きのこと。鼻がでんぐり返るようにむける。鼻柱が顔の中へ入って代わりに鼻の穴が出てくる。鼻むけともいう。
〈鼻返り〉のこと。(→ 鼻返り)
下唇が上下させることで、口の開閉を表現する仕掛け。しゃべっている表現をリアルに表現できる。
下アゴが、コメカミあたりから落ちるように口が裂け、物凄い鬼女の形相となるカラクリ。 山姥などにつかわれる。
ペロリと舌をだす首の仕掛け。丁稚の役によく用いられる。
振り乱した頭髪の間から、角が出る仕掛け。酒呑童子、山姥などにみられる。
頭が真二つに割れるカラクリ、立回りに使用される。割れた断面は、赤色の目玉や、白く描かれた口が、梨を割ったようになる滑稽な表現となっている。
→ 梨割りの首の画像
首のウナヅキを表現する鯨歯を使った古式のカラクリ。 胴串の後部に出た引栓で操作する。
首を斬られたとき、首桶に入れられて舞台へ出てくる首。小道具の部に入る。
◆次のページを見る 【文楽人形の首の種類】
参考文献 |
「文楽」 山田庄一 1991(1990) 「カラー文楽の魅力」 吉永孝雄 1974 |